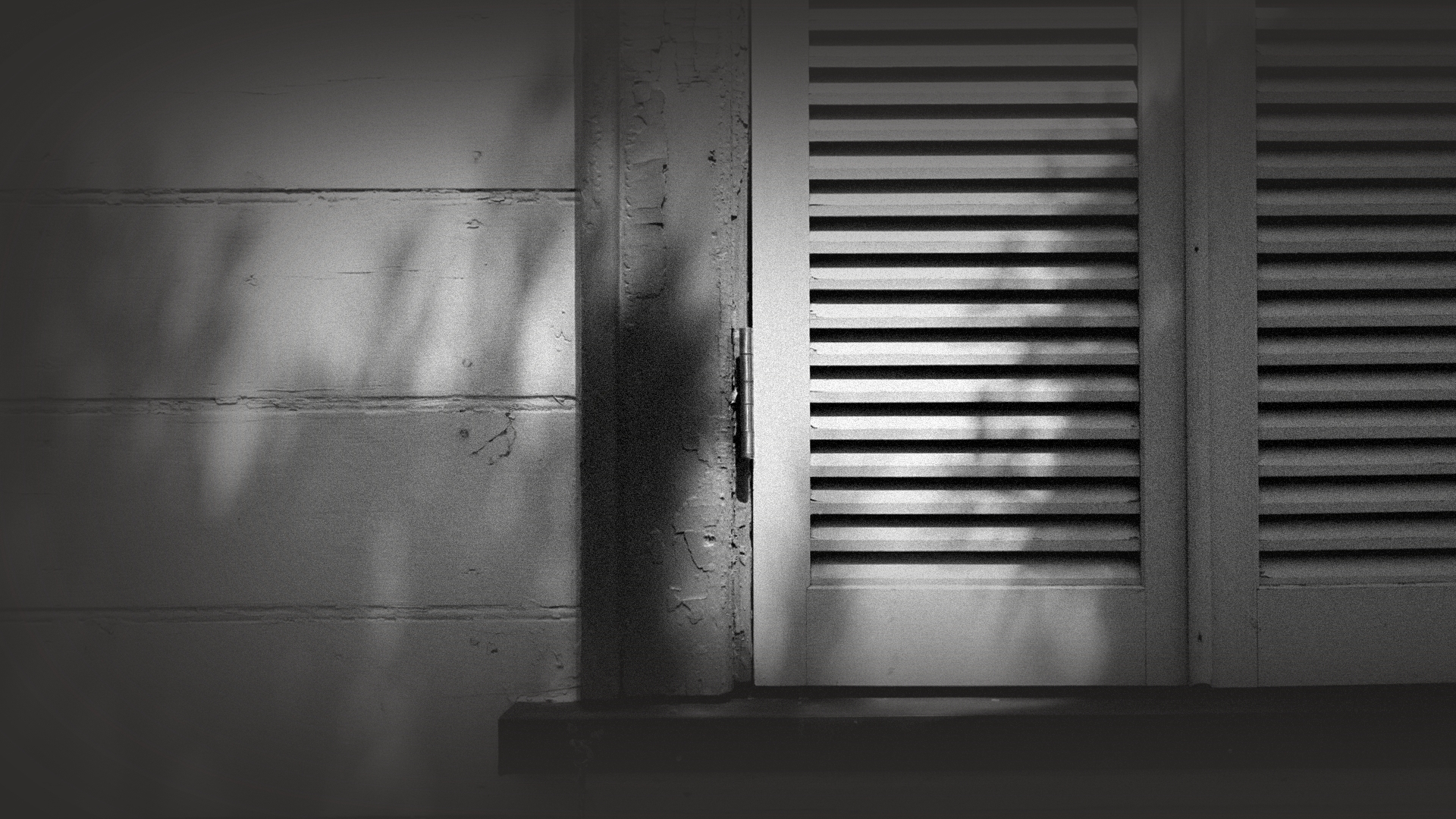鎌倉の未来に残す風景
鎌倉といえば“古都”としてのイメージが強いかもしれません。けれど実際、鎌倉駅周辺に“古都らしい風景”がどれだけ残っているかと問われると、私たちはそこに疑問を感じざるを得ませんでした。だからこそ考えたのです。
趣ある建物を100棟生み出すことができれば、その波及効果によって、“誇れる鎌倉の風景”が形成されていくのではないか。もちろん、それには50年、あるいは100年という時間がかかるかもしれません。実現する頃には、私たち自身はもうこの世にいないかもしれません。
それでも、このまちの未来にとって必要なことだと信じて、今できる一歩を積み重ねていきたい。そうした思いから、私たちはこの取り組みを始めました。


収益性と文化的価値の両立
全国各地で問われる共通の課題
古民家や文化財の保存には高額な維持管理費用がかかり、その多くが私有地として所有されています。相続が発生した際、遺産として受け継いだ家族や個人にとって、文化財を維持し続けることは大きな負担となり得ます。経済的な観点から見れば、取り壊しという選択肢が現実味を帯びてくることも少なくありません。
そのため、古民家や文化財の保存と活用を推進するには、地域社会全体での取り組みが欠かせません。地方自治体の支援や、地域住民との合意形成が重要な要素となります。自治体は、文化財を保護するための財政支援だけでなく、地域住民との協力体制を築く役割も担っています。地域の誇りであり、歴史の象徴でもあるこれらの建物を守るために、自治体の積極的な関与が求められています。


活用の視点が
保存を可能にする
私たちもまた、民間企業として、理念や文化的意義だけでは事業を継続できない立場にあります。文化財を長期にわたり保存するためには、それを支えるだけの収益構造を確立する必要があります。
文化庁が近年提唱する「文化資源の高付加価値化」にもあるように、文化財は単に保存するだけでなく、地域の人々や観光客とその魅力を“共有する場”として活用されることが、結果として保存の持続可能性を高めるとされています。
旧加賀谷邸のように、文化的価値をもつ建物を活用する際も、私たちは立地や用途特性を踏まえ、飲食店としての再生がもっとも有効であると判断しました。
とりわけ鎌倉のように観光需要に繁閑差がある地域では、季節や曜日に左右されず安定した運営を行うために、地域に根ざしつつ話題性や集客力のある機能を併設することが望ましいと考えました。これは単なる収益性の追求ではなく、文化財の自立性と持続性を確保するための現実的な手段であると私たちは捉えています。
歴史的文化財の保存と活用
誰のための保存なのか
旧加賀谷邸の再生にあたっては、地域の方々との関係性を築くことが、私たちにとって大切なテーマのひとつでした。このプロジェクトは、単なる収益を目的とした事業ではなく、歴史的建築物を保存・活用し、まちの文化や景観に貢献することを目指した取り組みです。
しかしながら、その意義や想いを地域全体で共有していくことには、時間と対話が必要であると実感しています。
旧加賀谷邸は、その立地と歴史的背景から、地域にとっても特別な存在です。だからこそ、建物の再生にあたっては、近隣住民の皆さまのご理解とご協力が欠かせませんでした。
一方で、文化財の保存や活用を巡る取り組みは、時に民間だけでは担いきれない課題も含んでいます。社会的意義のあるプロジェクトであっても、地域の皆さまの想いや行政との連携が欠けてしまえば、意図した価値が実現しにくくなることもあります。
文化や景観を未来に残していくためには、民間・地域・行政がそれぞれの立場を超えて協力していくことが何より重要だと、私たちは感じています。
文化財は「残す」ことだけでは守りきれません。
その価値が社会に理解され、活かされてこそ、次の世代へと自然に引き継がれていきます。
保存と活用、その両立をどう実現するか。これは一つのプロジェクトに限らず、全国の地域や自治体、民間事業者にとって共通の問いです。
私たちは、文化を残すために“稼ぐこと”を避けず、むしろ社会にひらかれたかたちで文化財を活用するという、新しい保存のあり方を模索していきます。